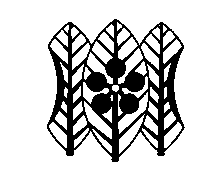
1年生を対象とした、メディア教育講演会が実施されました。学校やクラスの雰囲気にも徐々に慣れてくる頃は、学校の内外を問わず人間関係のトラブルも増える時期でもあります。特にSNSに絡むトラブル等は未然防止のための注意喚起が一番です。お互いが楽しく有意義な学校生活を送るためにも今回の講演会は、有効だったと思います。具体的な事例や数字を挙げて、内容もとてもわかりやすいものでした。
恒例の吹奏楽部による、昼休みコンサートが行われました。新入生の歓迎と部活動紹介を兼ねています。今月29日に行われる、「緑岡高校第16回定期演奏会」に向けて、音がかなり整ってきたようです。
本校の昼休みの日常的な光景です。中庭の緑の美しい季節になってきましたので、お弁当を持ち寄って青空の下でいただくのもまた格別です。1年生280名が入学して一週間が経過しましたが、表情も柔らかくなってきたようです。同窓会から寄付していただいた木製のベンチは、いつも一杯です。
入学生を歓迎するために、生徒会が中心となって企画した「対面式・新入生歓迎会・部活動紹介」が実施されました。2,3年生が先に入場した体育館に、新1年生が拍手に包まれて入場。生徒会長による生徒会会則が読み上げと歓迎の言葉によって、「学校は自分たちの手で作っていく」という決意を、新入生も新たにしたことと思います。緑岡高校には運動部文化部合わせて30の部活動がありますが、各部活動の紹介は、持ち時間の中で工夫を凝らして行われました。全員が何らかの部活動に加入して、高校生活を更に輝きのあるものにしてほしいと思いました。最後は、新入生代表によるお礼の言葉で締めくくられました。
「令和6年度入学式」が行われ、新たに280名の新入生を迎えました。満開の桜の中、新1年生が晴れやかに「緑高生」としてのスタートを切りました。一日一日を大切にして、健康で充実した高校生活を送ってください。
4月8日に「令和6年度新任式・表彰式・始業式」が行われました。「新任式」では、本年度本校に来られた8名の方々を紹介しました。「表彰式」では、棋道部並びに高校生科学研究発表会の表彰を行いました。昨年度の実績ですが、本年度最初の表彰になりました。
「始業式」では、失敗すら糧とする「したたかさ」、信念を持ちつつ多様なものの見方考え方を受容できる「しなやかさ」を身につけた、自他の「しあわせ」を願える人になってほしいという話をしました(緑高3S)。また、「タイムマネジメント」を意識した切り替えの重要性、学校内外で活動する際の「緑高生としての品位」についても、強く意識し、実践してほしいと思います。
























