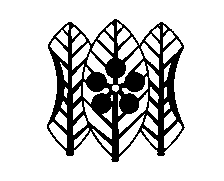
本校のテーマ
「未来を拓く科学的知見を創造し、世界のさきがけとなる人材育成」
平成25年度から5年間文部科学省からSSH「スーパーサイエンスハイスクール」に指定されました。SSHの指定を受けた学校では、科学技術系人材育成のため、各学校で作成した計画に基づき、独自のカリキュラムによる授業や、大学・研究機関などとの連携、地域の特性を生かした課題研究など様々な取り組みを行います。
本校では、課題研究などの探究活動や地域の教育資産の活用をとおして、「未来を切り開く科学的知見を創造し、世界のさきがけとなる人材の育成」を目指し、日本の理数教育のモデルとなるカリキュラム開発(さきがけプロジェクト)行うことを目的として実施します。
本校SSH3つの教育活動 その目標と仮説
【基盤教育】
<目標1>自然の事物現象を科学的,数学的に考察することができる。
→1学年の学習において,理科や数学の授業を中心に学習内容と実生活
との関連づけを行ったり,探究的活動を授業に取り入れることで養うこと
ができる。
<目標2>様々な情報に対して,客観的事実を元に批判的思考ができる。
→学校設定科目や講演会・特別講義などをとおして,多くの知識や考え方
が身につき,それをもとに課題研究を行うことで,養うことができる。
【専門教育】
<目標3>思考力・判断力・表現力が身につく。
→横断的な学習活動を行うことで,専門的知識と考え方を有機的に結合し,
また,課題研究やその発表会の実施,論文の作成をとおして培うことが
できる。
<目標4>自ら課題を設定し,問題解決ができる。
→「SS課題研究」の探究活動の中で,テーマを深く追究したり,多角的・
多面的に捉えることで,培うことができる。
【グローバルリーダー教育】
<目標5>グローバルなものの見方や考え方が身につく。
→最先端の研究者や大学の研究室での体験で身につく科学の広がりと,海
外研修やそのための事前事後の活動をとおして身につく国際性により育
成される。
<目標6>リーダー性が備わる。
→各種イベントの企画運営を行うことや同世代・異世代とのコミュニケー
ションをとる中で備わる。
◎上記のことにより,次の3項目が可能になる。
・国際高校生科学研究発表会 in MITO の開催(生徒による企画・運営)
・科学オリンピック国内本戦出場
・学会発表及び国際的な学会誌への論文投稿
延いては,「未来を拓く科学的知見を創造し,世界のさきがけとなる人材の育成」になると考える。


